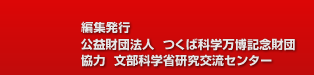筑波大学は11月14日、同大学生命環境系の竹下典男助教と、ドイツ・カールスルーエ工科大学の研究グループがカビの一種の糸状菌をモデルに、超解像顕微鏡を使って細胞の極性が維持される機構を可視化することに成功したと発表した。こうした糸状菌の解析は医薬や農薬開発での応用につながると期待される。
■医薬や農薬開発での応用へ期待
超解像顕微鏡は、数年前から使われだしているレーザー利用のいわば次世代の顕微鏡。光学顕微鏡で見ることができる限界(解像限界)は、200nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)。それに対し、DNA(デオキシリボ核酸)、タンパク質、細胞膜などの生体分子や生体組織は、みな200nm以下の大きさ。光学顕微鏡では、それらを生きたまま観測するライブイメージングができず、別の観測手段がいる。
その対応手段の一つとして注目されているのが超解像顕微鏡で、20nm程度が解像できる装置が販売されており、既に生物学の研究論文に超解像顕微鏡で得られたデータが使われだしている。今回は、これまで光学顕微鏡で可視化できなかった細胞の極性生長の過程を糸状菌で可視化した。
細胞は、均一な球体ではなく、一般に不均一な形をしていて、内部の成分も偏って存在している。一方の端と反対の端とでは異なる性質を持っており、こうした細胞の極性に従った生長により機能に合った細胞が形成される。この極性があることで、プラナリアは切られても頭のあった方向に頭が、尾のあった方からは尾が再生する。尾があった方向に頭が再生することはない。
糸状菌は、極性を先端に維持することで成長できる。今回の観察では糸状菌の細胞膜上に極性マーカータンパク質が一時的に集合し、次に拡散する様子が見られた。これは、細胞内の微小管と細胞膜の相互作用より一時的に細胞の極性が確立され、続いて細胞内の膜小胞と細胞膜の融合で極性生長が起きる際に拡散したことを示している。これの繰り返しにより極性が維持され、極性成長が効率的に行われることが明らかになったという。
糸状菌には、動植物や農作物への感染で病原性を示すものがある一方で、醸造・発酵や酵素の生産に利用されている有用な菌種もあり、糸状菌の極性生長の機構の解析は医薬・農薬の開発などにつながると期待されるという。