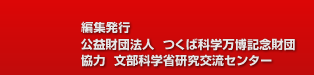筑波大学は1月13日、京都大学、東京大学などと共同で悪性リンパ腫の一種「末梢性T細胞リンパ腫」を発症した患者に特定の遺伝子異常が高い頻度で起きていることを突き止めたと発表した。この遺伝子は細胞の運動や生死を制御しており、遺伝子異常によってその機能が失われていた。これまで未解明な部分が多かった末梢性T細胞リンパ腫の診断・治療につながる成果という。
■診断・治療法の開発も期待
筑波大の千葉滋教授と坂田麻実子准教授、京大の小川誠司教授のほか、東京大学、癌研究会癌研究所、虎の門病院、総合病院土浦協同病院ほかの医師・研究者たちが参加する研究グループが突き止めた。
悪性リンパ腫は、ウイルスなど体内に侵入した外敵を排除する免疫の主な担い手であるリンパ球ががん化するもので、血液がんの一種。悪性リンパ腫のうち80%がB細胞リンパ腫で、遺伝子異常との関連はかなり解明されているが、残り20%の末梢性T細胞リンパ腫についてはまったく解明されていなかった。
そこで研究グループは、末梢性T細胞リンパ腫の患者6人の腫瘍組織と正常細胞からDNA(デオキシリボ核酸)を抽出、分析したところ、細胞内で細胞の運動や生死を制御する分子スイッチの役割を果たしている「RHOA遺伝子」に高い頻度で異常が見つかった。このため遺伝子の情報に従って作られるタンパク質の17番目のアミノ酸が、本来のグリシンからヴァリンに変わっており、分子スイッチとしての正常な機能が失われていた。
これを受けて、さらに約160人の末梢性T細胞リンパ腫患者の腫瘍組織からDNAを抽出して解析、遺伝子異常が現れる頻度を調べた。その結果、末梢性T細胞リンパ腫に限って60~70%以上という高い頻度で同じ遺伝子異常があることが分かった。さらにリンパ腫の発症プロセスについて、まず加齢によって前がん状態が生まれ、そこでRHOA遺伝子の異常が起こるという道筋も明らかにした。
研究グループは、今回の成果について「末梢性T細胞リンパ腫の画期的な診断法を提供するとともに、新規治療薬の創出も期待される」と話している。