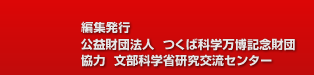筑波大学の村谷匡史准教授らは7月10日、ヒトの胎児期にだけ働く遺伝子が大人の胃がん組織で異常に活性化していることを発見したと発表した。微量の組織検体でも遺伝情報を統合的に解析できる手法を開発して突き止めた。この遺伝子を目印にすれば、がん細胞だけを攻撃したり探し出したりする新しい抗がん剤や診断技術の開発につながると期待している。
■新しい診断技術へ応用も
開発したのは、「クロマチン免疫沈降法」と呼ばれるDNA(デオキシリボ核酸)解析手法を高速DNA解析装置と組み合わせた手法。ごく微量の組織検体のDNAを効率よく増やして解析できる。特に、DNAの塩基配列で記録された「ゲノム(全遺伝情報)」と、その働きをDNAに結合したタンパク質などで制御している「エピゲノム」を統合的に解析できるのが特徴。
今回、成人から採取した胃がん組織の解析に新手法を利用、DNAに結合しているタンパク質の化学変化などを調べた。その結果、①ヒトの発生初期(胎児期など)に重要な働きをする一連の遺伝子が再活性化している、②遺伝子の異常な活性化は、通常は使われていない遺伝情報読み取り開始に関係した領域の働きで起きる―ことが分かった。
この結果は、大人の胃がん組織では普段機能していないゲノム領域が働き、通常とは異なる部分から遺伝子を読み出していることを示しているという。このことから、健康な大人には不必要な遺伝子が異常に活性化、がんを発生する原因になっている、と村谷准教授らはみている。
がん患者から採取できる臨床組織検体は、サイズが小さく、これまではDNAに結合したタンパク質などによるゲノム制御の様子を解析することは難しかった。今回、ゲノム・エピゲノムの統合的な解析が可能になったことで、変異を起こした遺伝子の制御に関与するゲノム領域の特定と変異の状態が同時に解析できるようになった。